変身(新潮文庫) [85回参照されました]
とくこさん がこの本を手に取りました。とくこさんは、これまでに46冊の本を読み、11,505ページをめくりました。
本の紹介

100% [全137ページ]
状態 読み終わった!
2015/05/09 18:00:45更新
著者 フランツ・カフカ ブックリンクされた本
-評価
★★★★★感想
苦しい。
感想がまとまらない。
家族、仕事、過去と未来。これから。
こんなに苦しいのは、私が未来よりも過去に意味を見出しているからだろうか。
グレーゴルとは何か、という答えは、読む人、読むタイミングによって変わるのだろうな。
グレーゴルは鏡みたい。
読書の軌跡
| 63ページ | 2015/05/09 00:34:27 | おれは本気になって、先祖から伝わった家具を居心地よく配置している暖かい部屋を洞窟に変えてしまおうと思っているのか。家具が全部片づけられてしまえばどこであろうとむろん思いのままに這いまわることはできるのだが、しかしそれと同時に人間として生きてきた自分の過去を急速に完全に忘れてしまうであろう。現にいまもう忘れかかっているのではなかろうか。そして母親の声をひさしぶりに耳にしたからこそ一時おれが正気にたちもどったのではあるまいか。 |
| 82ページ | 2015/05/09 16:59:05 | 移転を妨げていたおもな理由はむしろ完全な絶望感と、自分たちは親戚知人のあいだにもたえてその例を見ることのできないような不幸に見舞われているのだという考えとであった。(中略)父親を寝かしつけて、母と娘とが茶の間にもどってくる。そして仕事には手をつけず、頰と頰とが触れあわんばかりに寄りそってすわる。すると母親はグレーゴルの部屋を指さして、「グレーテや、あそこの戸をお締め」と言う。グレーゴルはいまやふたたび暗闇の中にうずくまる。隣の部屋では女ふたりがさめざめと泣くか、あるいは涙も出ずにテーブルをじっと見つめている。そんなとき、グレーゴルの背中の傷は、いましがた受けたばかりの傷のように痛みはじめるのであった。 |
| 91ページ | 2015/05/09 17:18:35 | グレーゴルは妙な感じをもったが、食事中のありとあらゆる物音の中からたえず聞こえてくるのはものを噛む歯の音であった。その音はグレーゴルにたいして、ものを食べるには歯というものが必要であり、かつどんなにりっぱな口でも歯がなければなにをすることもできないのだという事実を教えるために聞こえてくるように思われた。グレーゴルは心配そうにつぶやいた。「おれもなにか食いたい。だが、あんなものはいやだ。紳士諸君はあんなふうにしてめしを食っているというのに、このおれは死んでいくのだ」 |
| 94ページ | 2015/05/09 17:36:51 | だがしかし妹はじつに美しくひいていた。顔を片方に傾け、目は吟味するように、もの悲しく楽譜の行を追っている。グレーゴルはさらに少々にじりでた。そして床にぴったりとついてしまうほど頭を低く下げた。できることなら妹の視線をとらえようというのである。音楽にこれほど魅了されても、彼はまだ動物なのであろうか。グレーゴルは自分が憧れ求める未知の滋養分への道が示されているような気がした。彼は妹のすぐそばまね進んでいってスカートの裾をくわえ、それによって自分が妹ヴァイオリンを持って向こうの部屋へ来てもらいたがっているのだということをほのめかそうと決心した。実際ここではグレーゴルがしようと思うほどにはだれも妹の労をねぎらいはしないのだ。そうだ、そうしたら妹をもうおれの部屋から外へは出すまい。すくなくともおれの生きているあいだは。おれの恐ろしい姿はそのときはじめておれの役に立ってくれるだろう。部屋のどのドアをも油断なく同時に見はって、侵入者にはわっと吠えて向かってやる。もっとも妹を強制的におれの部屋にとどまらせておいてはならない。妹には寝椅子の上のおれの横にすわってもらう。耳をおれの頭のほうへ傾けさせる。そうしたらおれは、妹を音楽学校にやる堅い決心をしていたのであって、もしこんどの不祥事が勃発しなかったならば去年のクリスマスにーークリスマスはやっぱりもう過ぎさっしまったのだろうーーどんな反対論にも耳を貸すことなくみんなにこの計画を披露してやるところだったのだということをうちあけよう。こううちあけられてみれば、妹は感動のあまりわっと泣きだすだろう。そうしたらおれは妹の肩のところまで伸びあがって、首に接吻してやるのだ。勤めに出るようになってから、妹はリボンも襟もつけずに首を丸出しにしているのだから。 |
| 104ページ | 2015/05/09 17:51:37 | 感動と愛情をもって家の人たちのことを思い返す。自分が消えてなくならなければならないということにたいする彼自身の意見は、妹の似たような意見よりもひょっとするともっともっと強いものだったのだ。こういう空虚な、そして安らかな瞑想状態のうちにある彼の耳に、教会の塔から朝の三時を打つ時計の音が聞こえてきた。窓の外が一帯に薄明るくなりはじめたのもまだぼんやりとわかっていたが、ふと首がひとりでにがくんと下へさがった。そして鼻孔からは最後の息がかすかに漏れ流れた。 |
| 137ページ | 2015/05/09 18:00:45 |
コメント
コメントするにはログインが必要です。
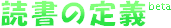
 ユーザー登録(無料)
ユーザー登録(無料)